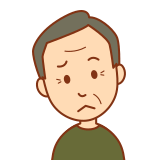
実際にどのように権利が移動するのか・・・。

権利変換計画の認可以降に権利は移動します。
そのプロセスについて説明します。

このページは現役の再開発プランナーが作成しています。
 |
改訂3版 わかりやすい都市再開発法 [ 都市再開発法制研究会 ] 価格:2090円 |
![]()

権利変換計画の決定と認可
権利変換計画書の原案を作成し、組合総会の議決を得て、審査委員の過半数の同意を得た上で、権利変換計画を定めることになる。
権利変換計画が確定した場合には、知事の認可を受け、認可を受けたら施行者は公告し、関係権利者に通知する。
以下が認可へ至る標準的なフロー。

権利変換期日
権利変換計画では、権利変換期日が定められる。
権利変換期日というのは、権利変換計画に定めた権利の変動が発効する第一段階の日である。
すなわち、この日において再開発地区の現況は何一つ変わっておらず、もちろん着工もしていないのに、事業が完了したときを想定して権利について移動が行われる。
権利者に関するすべての権利変換が権利変換計画に定められた内容通りに一括して行われる日となる。
新しい建物は実際には、この日に形がないが、権利の上では各々新しい権利に置き換わったことになる。
資産に関する補償
評価基準日に算定した補償対象額に権利変換計画の認可の公告日までの物価変動修正率を乗じた額を補償額として、権利変換期日までに施行者は支払いをしなければならない。
また、公告日以降は、実際に補償金が支払われるまでの間、年6%の利息相当額を上乗せすることになる。
明け渡しに関する補償
工事を開始する段階になると、施行者は、必要に応じて30日以上の期限を切って、地区内の権利者に土地の明け渡しを請求することができる。
この明け渡しに伴う補償をする。補償金の額は施行者と各権利者が協議して定め、明け渡し期限までに施行者は支払わなければならない。
権利の移動
権利変換期日における権利の移動は次に示すとおりである。
1)土地の所有権
施設建築物の敷地は、権利変換期日において一筆の土地となり、土地の所有権者には、施設建築敷地の共有持ち分の損失補償として、施設建築物の一部が与えられる。
2)借地権
従前の借地権は権利変換期日において消滅し事業完了後、施設建築物の一部が与えられる。
3)建築物の所有権
従前の建築物は、権利変換期日において一旦施行者に帰属し、事業完了後に施設建築物の一部が与えられる。
実際の工事が始まり土地の明け渡しが必要となるまでは、従前使用者が使用して問題ない。
4)借家権
従前の借家権は、権利変換期日において消滅し、これに代えて、事業完了後に従前の家主に与えられる施設建築物の一部について、借家権が与えられる。
なお、従前の家主が権利の変換を希望しないときは、施行者が従前の家主に代わって、借家人の家主となる。
5)配偶者居住権
従前の居住建物に設定された配偶者居住権は、権利変換計画に存続期間を記載し、権利変換後の施設建築物に同一の存続期間で継承される。
6)土地及び建物に関するその他の権利
地役権等の用益権は、権利変換期日において消滅し、これに対して補償が支払われる。
また、抵当権等については、その目的である権利の変換に応じて、新しい権利の上に移行する。



コメント