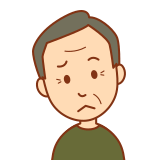
実際・・・どのような勉強をしてたの?

私の勉強方法はシンプルでとにかく繰り返すタイプです。
今回は、資格受験時の勉強方法や勉強時期について説明します。

このページは現役の建築設備士が作成しています。
![]()
![]()


第一次試験(学科)
私は、時間を決めたほうが長く持続する性格なので、試験を受けるのにあたって、勉強を1日のうち、いつするかを考えました。
そして、曜日関係なく、勉強開始前より朝1時間早く起きて、1時間勉強することにしました。きりが悪いと嫌なので1時間で勉強が完結するような勉強教材を作ることにしました。
勉強教材は、過去問題5年分を1問1答形式に分解し、建築一般、法規、設備の3種類に分け、かつ、類する問題ごとにまとめました。作業は1月から始めて2月までの2か月間かかりました。
3月は作成した教材を活用し、1問1答形式で5周くらい繰り返しました。テンポよく回答することを心がけることで、漠然と答えても必ず正解できるジャンル、必ず間違えるジャンル、考えればわかるジャンルが明確になりました。
また、幸いなことに、必ず間違えるジャンルを捨てても合格点に達することがわかったので、そのジャンルは4月以降は全く勉強しませんでした。
4月は、3月に判明した考えればわかるジャンルの理屈などをしっかり習得できるように、とにかく調べ続けました。
5月は、1問1答に戻り、捨てたジャンル以外を繰り返しました。間違いたら止まり、調べて理解をしてから進むようにしました。3周するころには、捨てたジャンル以外は全く間違えなくなったことを覚えています。
基本的には、1問1答を繰り返しているので、試験時間を意識して問題を解いたのは、前日のみで、試験受験前年度の問題を解きました。
合格基準点に少し達しないくらいの点数だったと思います。そもそも、捨てたジャンルのことを考えると、合格基準点を少し超えるくらいの勉強しかしていないので、十分な手応えでした。
試験結果は合格基準点をわずかに超える程度でした。
第二次試験(設計製図)
学科試験の解答速報確認後に勉強を開始しました。
様々な問題パターンが知りたかったので、総合資格学院に通学しました。通学者は圧倒的少数派だと思います。日曜は数時間総合資格で講義を受けますが、その他の曜日は学科に引き続き朝1時間の勉強を続けました。
他の勉強方法としては、日本設備設計事務所協会連合会が主催する講習会があり、受験生の半数くらいが参加していると思います。申込みは同連合会のホームページからできますが、申込み開始と同時にすぐに定員いっぱいになってしまうはずです。ですが、講習会のテキストのみ購入もできたはずです。
総合資格学院に通学しようと思った理由として、問題パターンの他に、全ての図面について、書き方から読み解き方まで教わり、あまり関わったことない設備図でも身に着けることができると思ったからです。
また、記述の部分についても、問題を解く過程で、多くのパターンを自分の中に用意できたと思っています。



コメント